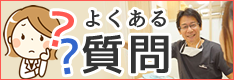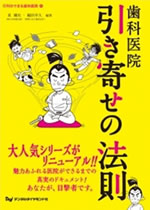2018/11/02
歯周外科の勉強会
皆さんこんにちは!千種区たなか歯科クリニック 歯科医師の島田 実果です。
先月、東京で歯周外科についての勉強会に参加してきました。
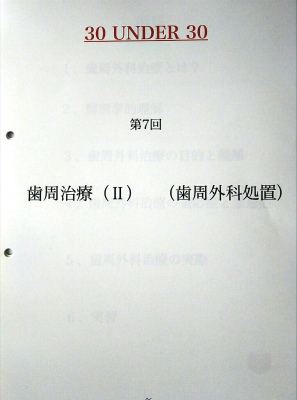
歯を失う原因の第一位は歯周病です。
歯周病は、細菌の塊(バイオフィルム)にある歯周病菌が原因で起こる、歯肉や歯槽骨(あごの骨)など歯周組織の病気です。代表的な症状としては、ブラッシングの際の出血、歯ぐきからの膿や口臭の悪化などです。
日本では35歳以上の約99%が歯周病にかかっているとされ、進行すると、最後には歯が抜け落ちてしまう恐ろしい病気です。 歯周病は、静かに痛みもなく進行していくため、「サイレントキラー(静かな殺し屋)」とも呼ばれています。歯周病は感染症のため1本の歯だけにとどまらず、お口の中全体に菌が広がっていきます。
今回学んだ歯周外科は、歯周病が進行して、歯石がポケットの深いところに入り込んでいて除去できず、スケーリングやルートプレーニングの治療で改善が見られなかった部分に対して行うことがあります。
具体的な方法は次のようになります。
1.フラップ手術
治っていない場所の歯ぐきを部分麻酔し、その後に剥離(切って開く)し、スケーラーの届かなかった部分の歯石や根の表面の汚れを取り除きます。取り除いた後は、開いた歯ぐきをきちんと閉じて縫合します。糸を抜くのは1週間程度後になります。手術後は痛み止めや化膿止めをしっかり飲みます。
2.歯周組織再生療法
通常の歯周治療では、失われた歯周組織を元通りの状態に戻すことはできません。その歯周組織を元通りにする「再生」を期待する治療法です。これには、特殊な膜を用いるGTR 法(歯周組織再生誘導法)とエナメルマトリックスタンパク質を主成分とした材料(エムドゲイン®)を用いる方法とがあります。エナメルマトリックスタンパク質は、歯が生えてくるときに重要な役割をするタンパク質です。
3.プラスチックサージェリー(歯周形成外科手術)
この手術は、見た目や機能の問題がある歯ぐきの形態などを整えることを目的に行うものです。ポケットをなくしたり組織を再生する目的の手術とは術式も異なります。
積極的な歯周治療が終わっても、治療が完全に終わった訳ではありません。とても大切なこととして、定期的にお口の中、歯の周りの組織のチェックを受けること(メインテナンス)が必要となります。歯周病は再発しやすい病気ですので、場合によっては再度問題が見つかり、治療が必要となることもあります。メインテナンスの期間は、罹っていた歯周病の重篤度や患者さんの状態によっても異なります。
是非とも期間を決めて、毎日の的確な歯磨きと規則正しい生活習慣が出来ているかどうか、再発がないか、定期的にチェックを受けにいらして下さい。
たなか歯科クリニック
歯科医師 島田 実果
月別アーカイブ
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (8)
- 2018年9月 (8)
- 2018年8月 (9)
- 2018年7月 (7)
- 2018年6月 (9)
- 2018年5月 (8)
- 2018年4月 (9)
- 2018年3月 (9)
- 2018年2月 (8)
- 2018年1月 (18)
- 2017年12月 (19)
- 2017年11月 (19)
- 2017年10月 (21)
- 2017年9月 (20)
- 2017年8月 (17)
- 2017年7月 (20)
- 2017年6月 (20)
- 2017年5月 (21)
- 2017年4月 (20)
- 2017年3月 (21)
- 2017年2月 (19)
- 2017年1月 (18)
- 2016年12月 (20)
- 2016年11月 (21)
- 2016年10月 (21)
- 2016年9月 (20)
- 2016年8月 (19)
- 2016年7月 (21)
- 2016年6月 (17)
- 2016年5月 (19)
- 2016年4月 (18)
- 2016年3月 (18)
- 2016年2月 (20)
- 2016年1月 (19)
- 2015年12月 (17)
- 2015年11月 (17)
- 2015年10月 (16)
- 2015年9月 (17)
- 2015年8月 (16)
- 2015年7月 (21)
- 2015年6月 (20)
- 2015年5月 (19)
- 2015年4月 (20)
- 2015年3月 (21)
- 2015年2月 (18)
- 2015年1月 (19)
- 2014年11月 (7)
- 2014年10月 (9)
このページの上へ ▲