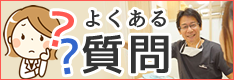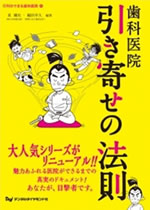2018/10/26
身近な顎関節症
皆さん、こんにちは。たなか歯科クリニックの歯科医師、岡島多翔幸です。
突然ではありますが、皆さんは顎関節症という疾患をご存知でしょうか。患者様の中には、顎関節症という言葉を聞いたことがある方も少なくないのではないかと思います。今日は、その顎関節症についてお話ししたいと思います。
顎関節症は、臨床的には、
1.顎関節および咀嚼筋等の疼痛(顎の関節や口を開け閉めする時に使う筋肉に痛みがある)
2.関節雑音(口を開けた時にカクッ、ザラザラと顎関節から音が出る)
3.開口障害ないし顎運動異常(口の開け閉めがしにくく、困難である)
の少なくとも一つの症状をみたし、他の顎関節疾患と明らかに異なる疾患のことを言います。
実は、顎関節症は、珍しい疾患ではありません。女性や若年者を中心として、非常に多くの患者様がみえます。かく言う私も顎関節症のうちの一人です。

それでは、顎関節症は、一体何が原因で起きるのでしょうか。顎関節症は、いくつかの分類の仕方がありますが(日本顎関節症学会の2001年の分類や2013年の分類があります。)、筋性のものと関節性のものに大別されます。
筋性のものは、口の開け閉めに関与する筋肉が緊張したりして、硬くなったりすることで起こります。また、関節性のものは、関節を構成する骨をはじめとする組織が原因になり、発症します。顎関節をつくる下顎の骨の一部のことを下顎頭と言いますが、この下顎頭には、関節円板という軟骨のようなザブトンが上に乗っています。正常な顎関節の方は、口を開けるときに、下顎頭とザブトンが一緒になって動くのですが、顎関節症の方の中には、ザブトンの位置がずれてしまって、正常に動いてくれないことがあるのです。このタイプの顎関節症の方は、関節性の顎関節症に分類されます。さらに、下顎頭の骨の形が変形してしまって発症する場合も関節性のものになります。
関節性の顎関節症の治療の基本は、消炎鎮痛薬の処方とスプリント療法になります。消炎鎮痛薬は、ロキソニンのような炎症と痛みを抑える薬です。スプリント療法とは、プラスチックでできたマウスピースを使って、咬み合わせを調整する治療です。
顎関節症は、先にもお話ししましたが、現代人にとって非常に身近な疾患です。私も顎関節症がひどくなったときは、咬み合わせがずれてしまい、いつも普通に食べれていたものが食べれなくなってしまった経験があります。
顎関節症は、実際に治療が必要なものは5〜6%とも言われており、頬杖やうつ伏せ寝、咬み締めやストレスの除去を行って生活習慣を見直したり、顎の運動療法をすることで(マニピュレーション)、自然に症状が治まってしまうことも多い疾患です。大切なのは、ご自身が顎関節症であると知り、正しい知識をもつことです。
もし、顎まわりが痛い、カクカク顎が鳴る、口が開けにくいといった症状でお困りの方は、一度ご相談ください。
たなか歯科クリニック
岡島多翔幸
月別アーカイブ
- 2018年10月 (8)
- 2018年9月 (8)
- 2018年8月 (9)
- 2018年7月 (7)
- 2018年6月 (9)
- 2018年5月 (8)
- 2018年4月 (9)
- 2018年3月 (9)
- 2018年2月 (8)
- 2018年1月 (18)
- 2017年12月 (19)
- 2017年11月 (19)
- 2017年10月 (21)
- 2017年9月 (20)
- 2017年8月 (17)
- 2017年7月 (20)
- 2017年6月 (20)
- 2017年5月 (21)
- 2017年4月 (20)
- 2017年3月 (21)
- 2017年2月 (19)
- 2017年1月 (18)
- 2016年12月 (20)
- 2016年11月 (21)
- 2016年10月 (21)
- 2016年9月 (20)
- 2016年8月 (19)
- 2016年7月 (21)
- 2016年6月 (17)
- 2016年5月 (19)
- 2016年4月 (18)
- 2016年3月 (18)
- 2016年2月 (20)
- 2016年1月 (19)
- 2015年12月 (17)
- 2015年11月 (17)
- 2015年10月 (16)
- 2015年9月 (17)
- 2015年8月 (16)
- 2015年7月 (21)
- 2015年6月 (20)
- 2015年5月 (19)
- 2015年4月 (20)
- 2015年3月 (21)
- 2015年2月 (18)
- 2015年1月 (19)
- 2014年11月 (7)
- 2014年10月 (9)
このページの上へ ▲