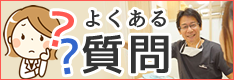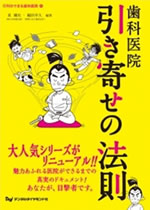2018/09/14
レントゲンについて
皆様こんにちは。
たなか歯科クリニック歯科医師の三輪万里子です。先日に引き続き今回も私がブログを更新します♪
歯科医院に来院し、皆さんが受ける検査として歯周病の検査(歯周ポケット測定)、虫歯のチェック、口の中の細菌の採取、そしてレントゲン検査があります。
今回はその中でレントゲン検査についてお話したいと思います。
当院で行うレントゲン検査としては以下の3つの方法があります。まず一つ目はパノラマ検査です。パノラマ検査は、歯やそれを支える顎の骨、顎関節など硬組織の病変を観察するために撮影される口全体を1枚におさめる広範囲なものです。撮影時には機械が顔の周りをグルリと回ります。
二つ目はデンタルレントゲン検査です。こちらは歯を1本1本観察するための小さい範囲のものです。歯と歯の間や、歯の根っこの先に炎症がないか、また歯石のついている部分も映り、細かい部分まで鮮明に写るため詳細な情報が欲しい場合に使われ一度に数枚とることもあります。
三つ目は歯科用のCT検査です。上記のパノラマ検査やデンタル検査など二次元の撮影では判断が難しい場合に行う三次元的な撮影です。例えば根っこの治療において炎症が根っこのどの部分のどれくらい進んでいるのか、上顎洞という鼻の近くの空洞まで炎症が広がってないか、インプラント治療が可能か判断するために骨の厚みや深さなどを知り安全に手術を行えるかなど、従来のレントゲン検査で分からない部分を知るためのものです。
CTと聞くと医科のCTが容易に想像できベッドに寝て狭い空間に入っていく大きな機械で撮影するイメージがありますね。しかし歯科用のCTは歯や顎の部分だけなのでパノラマ検査と同じ状態で撮影することができます。
ではこれらのレントゲン検査の被爆量はいったいどのくらい人の体に影響するのでしょうか。被爆というと嫌なイメージがあると思いますが、実は誰もが毎日生活をする中で自然と暴露しているものなんです。普段私たちが口にする食べ物からも出ていることもあります。食事による内部被ばくは年間平均410マイクロシーベルトといわれています。また、東京~ニューヨーク間を飛行機で往復するとおよそ200マイクロシーベルトの放射線を浴びることになります。
一方歯科のレントゲンは1回で1~8マイクロシーベルトなので、年に数回レントゲンを撮っても大きな被害を受けるとは考えにくいです。またレントゲンを撮る際には、鉛でできた防護エプロンをつけて撮影するので、必要以外のところに照射されないよう配慮もされています。このエプロンには特殊な加工がしてあり、放射線源の透過を緩和することができます。
私達の歯科医療機関で行われるレントゲン検査は、患者さんの現状や病態を知るために必要な検査になってきます。しかし妊娠中の方などレントゲン検査に制限がある方も中にはいらっしゃいます。何かご不明点やご質問があればお気軽にご相談くださいね。

千種区たなか歯科クリニック
歯科医師 三輪万里子
月別アーカイブ
- 2018年9月 (5)
- 2018年8月 (9)
- 2018年7月 (7)
- 2018年6月 (9)
- 2018年5月 (8)
- 2018年4月 (9)
- 2018年3月 (9)
- 2018年2月 (8)
- 2018年1月 (18)
- 2017年12月 (19)
- 2017年11月 (19)
- 2017年10月 (21)
- 2017年9月 (20)
- 2017年8月 (17)
- 2017年7月 (20)
- 2017年6月 (20)
- 2017年5月 (21)
- 2017年4月 (20)
- 2017年3月 (21)
- 2017年2月 (19)
- 2017年1月 (18)
- 2016年12月 (20)
- 2016年11月 (21)
- 2016年10月 (21)
- 2016年9月 (20)
- 2016年8月 (19)
- 2016年7月 (21)
- 2016年6月 (17)
- 2016年5月 (19)
- 2016年4月 (18)
- 2016年3月 (18)
- 2016年2月 (20)
- 2016年1月 (19)
- 2015年12月 (17)
- 2015年11月 (17)
- 2015年10月 (16)
- 2015年9月 (17)
- 2015年8月 (16)
- 2015年7月 (21)
- 2015年6月 (20)
- 2015年5月 (19)
- 2015年4月 (20)
- 2015年3月 (21)
- 2015年2月 (18)
- 2015年1月 (19)
- 2014年11月 (7)
- 2014年10月 (9)
このページの上へ ▲