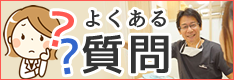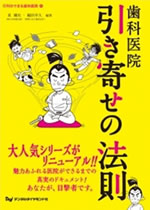2018/06/09
歯周病について
みなさんこんにちは!千種区たなか歯科クリニック 歯科衛生士の肆矢紗希です。
今回も前回に続き、歯周病についてお話ししていきますね!
歯周病というのは感染症で、歯の周りの組織への微生物(細菌)感染に対する生体防御反応の結果として引き起こされた炎症によって、歯ぐきの上皮や歯ぐきの結合組織、歯の靭帯の破壊、歯を支える骨(歯槽骨)の吸収が生じる病気です。
感染する微生物は、歯垢(プラーク)由来です。
そして、歯周病が発症した後もプラーク中の微生物による歯の周りの組織への侵襲が継続すると、炎症の範囲も拡大し、歯周病は進行していきます。
このプラークが歯の表面に付着すると、歯ブラシなどによる機械的な力でないと取り除くことは困難であるということは以前にもお話ししましたね!
歯周病の病気の具合は、その進行段階から「歯肉炎」と「歯周炎」に分けられるとお伝えしましたが、その進行スピードは、局所に付着している"プラークの量"やその侵襲を受けている"時間"、組織の"免疫応答の程度"で変化するため、場所によって病気の具合が異なるのです。
すなわち、歯周病の進行は、各部位ごとに細菌の集合体と宿主の反応のバランスとの相互作用で決定されるのです。
歯周病にかかりやすい因子を説明するものに、歯周病の危険因子(リスクファクター)の概念があります。
歯周病発症の危険性が最大になる条件は、
① 病原(微生物)因子:プラーク中の細菌のこと。プラークは歯ぐきに炎症を起こさせる直接的な因子で、歯周病の主 因または主要因子です。
② 環境因子:これには様々な生活習慣や嗜好、お口の中の環境などとともに口腔衛生への関心度なども含まれま す。特に、喫煙は歯周病の環境因子の中で最大の危険因子で、歯周病の重篤化や治療後の傷の治りが 遅くなります。また、薬物のフェニトイン(抗てんかん薬)、ニフェジピン(カルシウム拮抗剤、降圧 薬)、シクロスポリン(免疫抑制剤)などは副作用として歯ぐきの増殖を発現させることがあります。
③ 宿主因子:全身的な因子は、年齢や免疫応答、遺伝、全身疾患などで、様々な外敵に対する免疫応答などの防御 能力が含まれます。糖尿病や骨粗鬆症の患者さんでは、歯周疾患が増悪しやすいのです。
その他、この宿主因子の中に、歯周病の発症・進行に関係するお口の中の局所的因子として口呼吸や不適合な修復物、歯列不正、歯周組織に損傷を引き起こす噛み合わせなどがあります。
この3つが組み合わさると、歯周病発症の危険性が最大になるのです。歯周病の発症には多くの因子が関与していることがわかりますね!
私自身もまだまだ歯周病についてもっと詳しく勉強している最中です!
みなさんに歯周病について知っておいてほしいこと、まだまだありますので、次回の時にまたお伝えしますね!
千種区たなか歯科クリニック 歯科衛生士 肆矢紗希
月別アーカイブ
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (8)
- 2018年4月 (9)
- 2018年3月 (9)
- 2018年2月 (8)
- 2018年1月 (18)
- 2017年12月 (19)
- 2017年11月 (19)
- 2017年10月 (21)
- 2017年9月 (20)
- 2017年8月 (17)
- 2017年7月 (20)
- 2017年6月 (20)
- 2017年5月 (21)
- 2017年4月 (20)
- 2017年3月 (21)
- 2017年2月 (19)
- 2017年1月 (18)
- 2016年12月 (20)
- 2016年11月 (21)
- 2016年10月 (21)
- 2016年9月 (20)
- 2016年8月 (19)
- 2016年7月 (21)
- 2016年6月 (17)
- 2016年5月 (19)
- 2016年4月 (18)
- 2016年3月 (18)
- 2016年2月 (20)
- 2016年1月 (19)
- 2015年12月 (17)
- 2015年11月 (17)
- 2015年10月 (16)
- 2015年9月 (17)
- 2015年8月 (16)
- 2015年7月 (21)
- 2015年6月 (20)
- 2015年5月 (19)
- 2015年4月 (20)
- 2015年3月 (21)
- 2015年2月 (18)
- 2015年1月 (19)
- 2014年11月 (7)
- 2014年10月 (9)
このページの上へ ▲