ドライマウス
こんにちは、千種区覚王山 たなか歯科クリニック歯科衛生士の高山です。当歯科医院のブログへようこそ!春の訪れとともに、暖かな日差しが心地よく感じられる季節になりました。この時期は新しいスタートを切る方も多いかと思います。
花粉症や環境の変化で体調を崩しやすい時期ですが、口腔ケアも忘れずに行いたいですね。春は新しい生活が始まる時期でもありますので、ぜひこの機会に定期的な歯科検診をお考えください。

さて今回のブログではドライマウスについての話題です。
ドライマウス(口腔乾燥症)は、口の中が乾燥している状態を指します。通常、唾液の分泌が減少することで起こり、様々な原因があります。
### 原因
1. **加齢**: 老化に伴う唾液腺の機能低下。
2. **薬の副作用**: 一部の薬(抗うつ薬、抗ヒスタミン薬、高血圧薬など)が唾液分泌を抑えることがあります。
3. **病気**: シェーグレン症候群、糖尿病、パーキンソン病などの病気が影響を与える場合があります。
4. **放射線療法**: 頭部や首の放射線治療が唾液腺に影響を及ぼすことがあります。
5. **脱水症状**: 十分な水分摂取がない場合、口が乾燥することがあります。
6. **ストレスや不安**: 精神的な要因もドライマウスを引き起こすことがあります。
### 対処法
1. **水分補給**: 定期的に水分を摂取し、脱水を防ぐ。
2. **唾液促進食品**: 酸味のある食品(レモンなど)を摂取することで唾液の分泌を促進できます。
3. **唾液代用品**: 市販の唾液代用品(スプレーやガム)を利用する。
4. **口腔衛生の徹底**: 定期的に歯を磨き、口腔内の清潔を保つ。
5. **禁煙**: タバコは口腔乾燥を悪化させるため、禁煙が推奨されます。
6. **医師の相談**: 薬の副作用や病気が考えられる場合、医師に相談する。
7.**唾液腺のマッサージ**:唾液腺を刺激し分泌を促します。
ドライマウスは不快な症状ですが、適切な対策を講じることで改善できます。必要に応じて医師の診断を受けることも重要です。
###口の中への影響
ドライマウス(口腔乾燥症)は、唾液の分泌が減少することによって引き起こされる症状です。これにより、口腔内にはさまざまな影響が生じることがあります。
1. **口腔内の不快感**: 唾液が少ないことで口腔内が乾燥し、不快感や喉の渇きを感じることがあります。
2. **虫歯や歯周病のリスク増加**: 唾液には抗菌作用や自浄作用があり、口腔内のバイ菌の繁殖を抑える役割があります。唾液が減少することで、その効果が失われ、虫歯や歯周病のリスクが高まります。
3. **口臭**: 唾液が少ないと、食べ物の残渣や細菌の繁殖が進みやすく、口臭が発生する原因になります。
4. **嚥下障害**: 口腔内が乾燥していると、食べ物を飲み込みにくくなり、嚥下障害を引き起こすことがあります。
5. **口腔粘膜の炎症**: 唾液分泌が減少すると、口腔の粘膜が乾燥し、炎症を起こすことがあります。これは痛みや不快感につながります。
6. **味覚の変化**: 唾液が不足すると、味覚にも影響が出ることがあります。特に味を感じにくくなったり、苦味が強く感じることがあります。
この様に様々な影響があり、歯科医院での健診、相談をお勧めします。
たなか歯科クリニック歯科衛生士 高山
口腔がんについて
こんにちは、名古屋市千種区たなか歯科クリニック歯科衛生士の関谷です。
今回は口腔癌についてお話します!
口腔癌とは、舌や歯肉、頬粘膜、上顎の裏側や舌と下顎の歯茎との間にできる口腔底や口唇などお口の中に発生する悪性腫瘍のことを言います。
口腔癌の中で最も多いのは舌癌で、口腔癌全体の60%を占めています。
口腔癌の発生にはさまざまな要因が関与しており、まだ解明されていない点もありますが主に以下のようなリスク因子があります。
・喫煙と飲酒
喫煙は口腔内の細胞に長期的なダメージを与え、発癌リスクを大幅に高めます。タバコの煙には、多くの発がん性物質が含まれており非喫煙者と比べて喫煙者の口腔癌の罹患リスクは5.2倍とされています。
また、大量のアルコール摂取も口腔粘膜を刺激し、特に喫煙との相乗効果によって発症リスクが高まることが知られています。
・口腔内の不衛生
口の中や歯の汚れ、舌や粘膜についた白苔、未治療の虫歯、口の中の乾燥など、口腔内が細菌で汚染されていると口腔癌を発症しやすくなります。
・慢性的な機械的刺激
不適切な歯磨きや不潔な入れ歯の使用は、慢性的な刺激や炎症を引き起こし、口腔癌のリスクを高めます。
・ヒトパピローマウイルス
HPVへの感染は、口腔癌の発生に関与していると考えられています。
口腔癌の症状は、初期段階では自覚症状がほとんどないことが多いため、早期発見が難しい場合があります。
〇初期症状
口腔内の癌ができた部分の粘膜が赤くなったり、白色に変色したり、形が変わったりします。また、口の中に硬いしこりや腫れができることもありますが、初期にはほとんど痛みや出血を伴わないため、口内炎だと思い込んでそのまま放置してしまうケースも少なくありません。
2週間しても口内炎がなかなか治らない場合は注意が必要です!その他にも癌の進行に伴い、強い口臭が生じることがあります。
口腔癌の治療は、癌の進行度や患者さんの状態に応じて、腫瘍を外科的に切除したり、放射線の使用や抗がん剤を使用するなどの治療が行われます。
〇予防
・喫煙、飲酒
喫煙や過度な飲酒を避けることで、口腔癌のリスクを大幅に減らすことができます。
・口腔内の清潔を保つ
歯磨きを丁寧に行い、定期的に歯科検診を受けることで、口腔内の健康を維持し、癌のリスクを低減できます。
・定期的な歯科検診
早期発見・早期治療が最も重要です!
口腔癌は進行すると治療が困難になるため、異変を感じたらすぐに専門医に相談してみてください!

千種区たなか歯科クリニック 歯科衛生士関谷
知覚過敏について
みなさんこんにちは!たなか歯科クリニック歯科衛生士の川元です。まだ寒い日が続いていますがお身体に気をつけて過ごしてくださいね。
さて、今回は知覚過敏についてお話したいと思います。
知覚過敏か確かめる方法
1.冷たい食べ物や飲み物、温かい食べ物や飲み物が歯にしみる
2.甘いものがしみる
3.酸っぱいものがしみる
4.歯磨き中、毛先が歯に当たるとしみる
5.歯肉が下がって歯の根元が露出している
以上のことが当てはまると知覚過敏の可能性が高いです。
知覚過敏の原因
知覚過敏になってしまう原因として歯の本体である象牙質が露出することにあります。例えば、歯周病や加齢、不適切なブラッシング、歯ぎしり食いしばりなどが原因で歯肉が下がってしまい歯の根の部分の象牙質が露出してしまいます。
知覚過敏の改善方法
1.ブラッシング圧を弱くする
硬めの歯ブラシで強い力で磨くと歯肉を傷つけ知覚過敏になってしまいます。歯ブラシの硬さは柔らかめかふつうで毛先が多少しなる程度の力で磨くのがおすすめです。
2.キシリトールガムを噛む
唾液中にはカルシウムやリン酸などの歯の成分であるミネラルがたくさん含まれています。食事の時によく噛み、キシリトールガムなどで唾液を多く出すと溶けだしたミネラルを補うことができます。
3.知覚過敏用歯磨き粉を使う
知覚過敏用歯磨き粉には硝酸カリウムという薬用成分が入ってます。この成分が歯の神経の周りにバリアを作り知覚過敏を軽減させます。しみる症状が強いところには歯磨き後、知覚過敏用歯磨き粉を塗り込んでも効果があります。
4.フッ素ジェルを塗る
フッ素は歯の表面のミネラルと結びついて歯を硬くすることができます。歯磨き後にフッ素のジェルを塗り込むと知覚過敏が軽減します。
5.歯を食いしばるのをやめる
歯を食いしばると歯に亀裂が入ったり、歯の根元が削れて知覚過敏になります。日中食いしばりに気をつけることと夜寝る時はマウスピースを使うことで食いしばりを防止することができます。
6.歯科医院で治療してもらう
歯がしみるのは根元の象牙質が露出しているためです。しみる症状を抑えるためにプラスチックの詰め物で根元をカバーすることが可能です。ただし、歯ぎしりや食いしばりなどで負担がかかりやすい部位だとカバーが取れやすい場合があります。
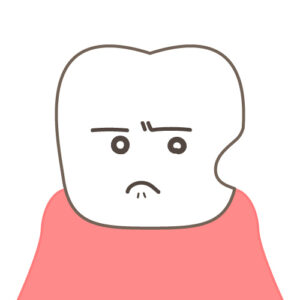
知覚過敏だと思っていたら虫歯だったという場合もあるのでしみる症状が長く続いていたり強くなっている時は歯科医院を受診してみてください。
名古屋市千種区たなか歯科クリニック歯科衛生士川元。
プラークとは?
こんにちは!名古屋市千種区 たなか歯科クリニックの冨里です。
今回は、お口の健康にとってとても大切な「プラーク」についてお話しさせていただきます!
歯科医院でよく耳にする言葉かもしれませんが、プラークがどのようなものなのか、
またどうやって予防するのかについて詳しくご紹介します。
プラークとは、歯の表面に付着する細菌のかたまりで、白くて粘着性のある薄い膜のようなものです。
食べ物や飲み物に含まれる糖分をエサにして、口の中の細菌が繁殖し、時間が経つことで歯にこびりつきます。
このプラークが蓄積すると、歯周病や虫歯など、さまざまな口腔トラブルを引き起こす原因となります。
朝起きたとき、口の中がネバネバしていると感じたことはありませんか?それはまさに
プラークが形成されているサインです。寝ている間に唾液の分泌が減少し、プラークが付着しやすくなるからです。
プラークは放置すると、どんどん硬化して「歯石」になり、歯ブラシでは取り除くことできなくなります。
歯石ができる前にプラークをしっかりと取り除くことが、虫歯や歯周病を防ぐために非常に重要です。
虫歯は、プラークに含まれる細菌が糖分を分解し、酸を産生することによって引き起こされます。
その酸が歯のエナメル質を溶かし、虫歯を進行させてしまうのです。
一度進行した虫歯は痛みを伴うこともあり、治療が必要になります。
また、プラークに含まれる細菌は歯茎にも悪影響を与えます。歯茎に炎症を起こし、歯周病が進行すると、
最終的には歯を支えている骨が溶けてしまうこともあります。
このように、プラークが原因で口腔内の健康が損なわれてしまうのです。
では、プラークを予防するためにはどのような対策を取れば良いのでしょうか?
以下のポイントを意識することで、効果的にプラークの蓄積を防ぐことができます。
1. こまめな歯磨き
毎日の歯磨きが最も大切です。食後や寝る前に歯を磨くことを習慣にしましょう。
特に、寝る前の歯磨きは重要です。寝ている間に口の中の細菌が増えるため、
寝る前にきれいに歯を磨いておくことで、プラークの形成を抑えることができます。
2. フロスや歯間ブラシの使用
歯ブラシだけでは、歯と歯の間の細かい部分まで十分に磨けないことがあります。
そのため、フロスや歯間ブラシを使って、歯と歯の間のプラークをしっかりと取り除くことが大切です。
これにより、歯周病の予防にもつながります。
3. 食生活の改善
食べ物の選び方も、プラークの形成に影響を与えます。特に甘いものや酸性の飲み物は、プラークを作りやすくします。
食後は歯を磨けない場合でも、口をすすぐだけでもプラークの予防になります。
また、野菜やフルーツなど、噛むことで唾液が分泌され、歯を守る効果があります。
4. 定期的な歯科医院でのチェック
定期的に歯科医院でプロフェッショナルなクリーニングを受けることも大切です。
歯科衛生士によるスケーリングで、歯石やプラークを取り除いてもらうことができます。
虫歯や歯周病の早期発見にもつながりますので、定期的なチェックをお勧めします。
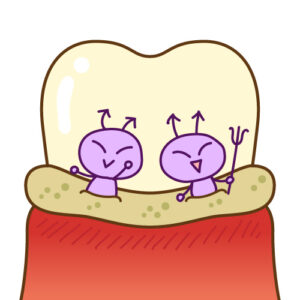
いかがでしたか?プラークは歯の健康を脅かす原因となる存在ですが、
毎日のケアをきちんと行うことで防ぐことができます。今日から意識して歯を大切にしてみてくださいね。
健康な歯を保つために、今日からできることを少しずつ始めていきましょう!(^^
名古屋市千種区 たなか歯科クリニック 冨里
できるだけ避けたい!「歯根破折」
こんにちは! 千種区たなか歯科クリニック 歯科医師の 満田 誠です。
今回のお話は「歯根破折」。
すなわち、“歯の根っこが割れてしまった” や “ヒビが入ってしまった” 状態を意味します。

その原因としては、“力”。もちろん、ぶつけた 転んだ などの外傷でも起こるのですが、どうやら 多くの場合は、“繰り返される咬合による 応力の蓄積によって起こる疲労破壊” から歯根破折が起こるようです。
歯根破折の怖いところは、治療の手段が 「原則として抜歯」 であること!!(>_<)
皆さまご存じの通り、歯を失う原因の第1位は「歯周病」 第2位は「虫歯」ですが……、実は第3位が「歯根破折」なのです!
歯の割れている部分が 歯冠(歯茎の位置より上の、歯の頭部分)に留まっていれば、被せ物にすることで補強して歯を残せるのですが、それが根まで割れてしまっていると 困難となります。
無理やり被せ物にしても、土台が弱いので すぐに取れてしまいますし、割れている歯根は段々炎症を起こして化膿してきます。やがて、その炎症によって周りの骨を溶かして弱らせたり、破折した歯根そのものが 隣の歯や歯周組織を巻き込んで症状が悪化していく 病因(感染源)となっていくのです。
そんな怖い歯根破折ですが、なにぶん歯茎の中に隠れている「根」は 目では見えないため、患者様がご自分で気づくことは稀です。多くの場合は、何らかの自覚症状があり、それがきっかけで検査をしたところ発見されます。
具体的にどんな症状かというと、
・歯茎が腫れている
・歯茎にニキビの様な できものがある
・歯がぐらつく
・被せ物がゆれる、取れた
・咬むと痛い
などです。
そして、どのような歯・どんな方に歯根破折が多いかと言うと、
・神経が無い歯(特に金属の土台が入っている歯、ブリッジの支台となっている歯)
・歯ぎしり・食いしばりの傾向がある
・咬む力が強い
などに破折のリスクが高くなります。思い当たる方、大丈夫ですか? ご心配であれば御相談くださいね♪
色々と歯根破折の問題点をお話ししましたが、ご安心ください! 以上の事をふまえれば、おのずと破折を避ける予防法も見えてきます。
まず、“神経を取らなければならないような 虫歯を作らないこと” は勿論です。
他には、神経の無い歯の被せ物は “金属の土台ではなく、グラスファイバーの土台を入れること”。金属よりグラスファイバーの方が柔軟性があり、歯に優しいため破折リスクを軽減できます。
そして、歯ぎしり・食いしばりがある方は、“日中は、自分で意識して その癖をコントロールする” 、“就寝中はマウスピースを使用する” ことで、過度な力から歯を守ります。
そして、硬い食べ物はお気をつけください! ちょっと食べやすくしてからの方が良いかも。
歯周病・虫歯と違って、なかなか意識しにくいけれど、実は身近にあって怖い「歯根破折」。大切な歯を失わないように予防していきましょう!
千種区 たなか歯科クリニック
歯科医師 満田 誠













